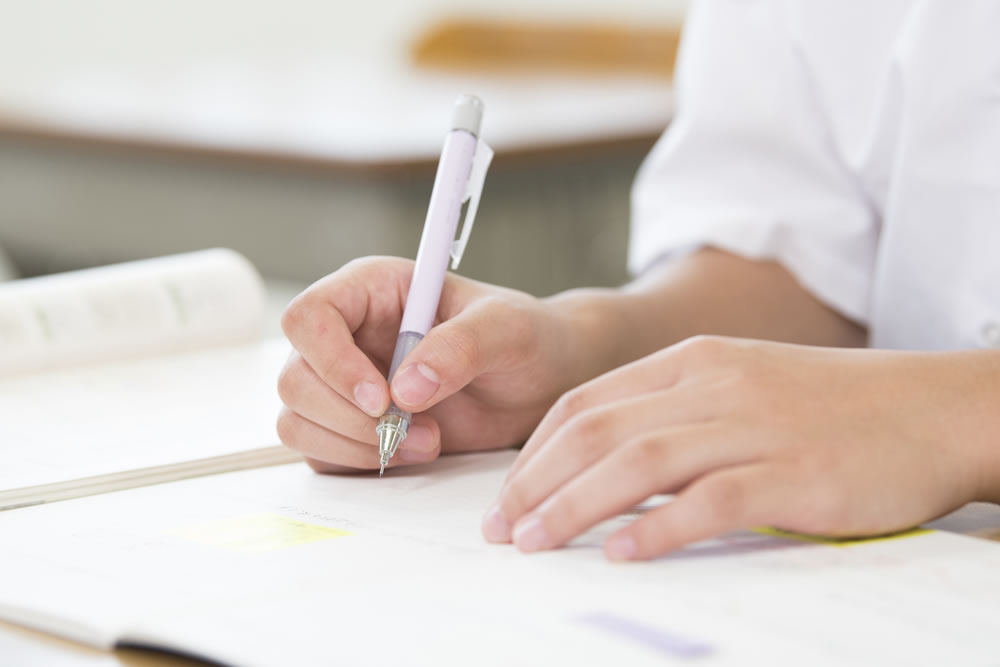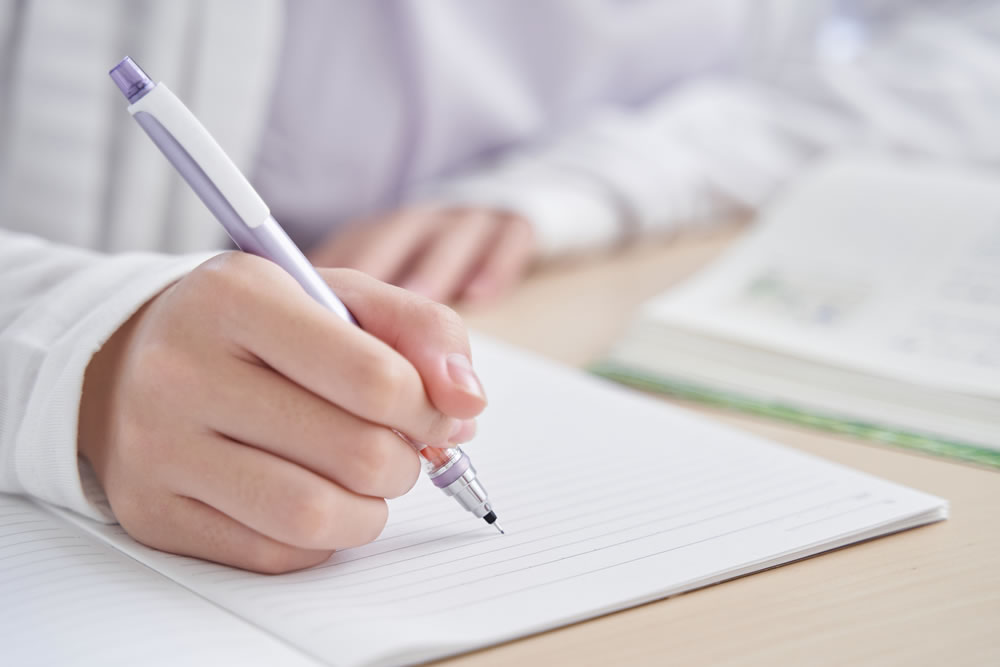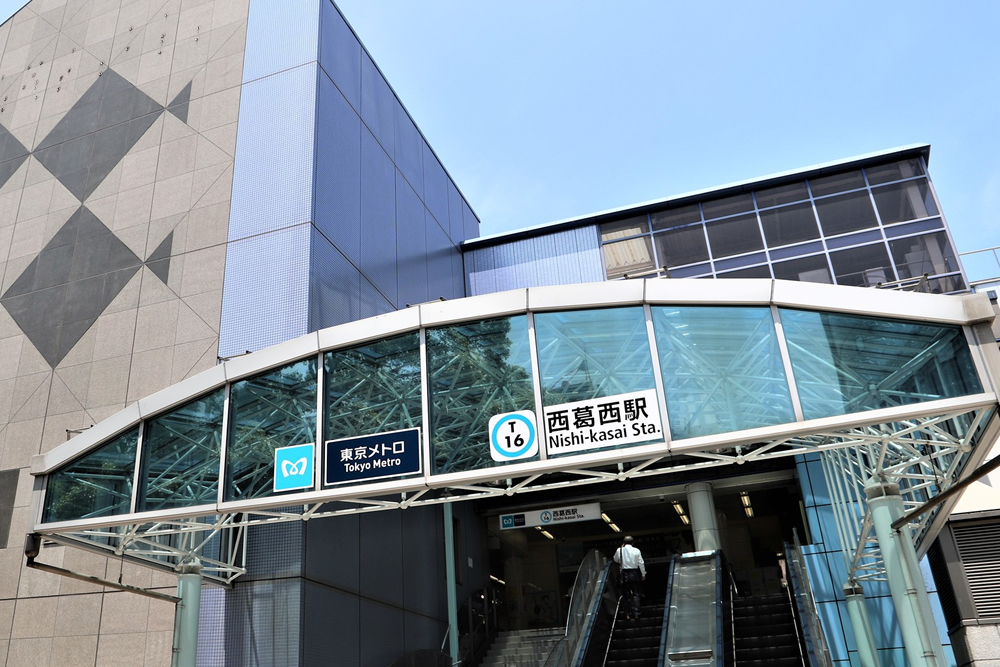このページは約 9 分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
目次
漢検とは
漢検(かんけん)とは、漢字能力を測るための試験で、正式名称を「日本漢字能力検定」といいます。漢検は、日本国内外で日本語や漢字を学習する人の漢字能力レベルを証明できる検定です。正確な漢字能力を身につけると基礎学力や文章の理解力の強化につながるため、漢検は入試で有利になると言われています。
ここでは、漢検の受験級の目安や受験するメリット、入試に有利になる等級を紹介していくので参考にしてください。
漢検の受験級の目安【学年別】

漢検の受験級は、「公益財団法人 日本漢字能力検定協会」によって、学年や年齢に基づいた目安が設けられています。下記の目安を参考にすることで、何級を受験すればいいかがわかりますが、漢字の学習には個人差があるので学年だけで判断する必要はありません。
ここでは、少し学年の幅を広げて受験級の目安を紹介します。
小学1〜2年生
通常、小1から小2の生徒が受験するのは9~10級です。この級では、小1から小2修了程度の漢字の読み書きや、意味を問う問題が出題されます。例えば、身近な物や動植物の漢字、基本的な動詞・形容詞などの漢字が対象です。
小学3〜4年生
小3から小4の生徒が受験するのは7~9級です。7~8級は小3から小4修了程度の難易度で、身近な話題や状況に関連した漢字が問われます。学校で習う漢字や基本的な表現に加えて、四字熟語やことわざなども含まれます。
小学5〜6年生
小5から小6の生徒が受験するのは5~7級です。5~6級は、小5から小6修了程度の広範囲な漢字が出題されるため、文章中での使い方や意味の理解が求められます。日常会話や文章によく使われる漢字や、一般的な学習内容が中心です。
中学生
中学生の場合、まずは4~5級を受験するでしょう。どちらの級も、中学校の教科書や日常的な文章で使用される漢字、熟語、慣用句などが問われます。文章中の漢字の意味や使い方、表現力も求められます。
漢検を受験する中学生は、3級を目指す生徒が多いです。これまでの試験に比べて問題の難易度は高くなりますが、3級を取得していると高校受験に役立てることができます。
高校生以上
高校生以上の受験者は、準2~3級以上を目指すのが一般的です。3級以上は、高校や大学入試の基準に近い内容で、幅広い分野の知識や論理的な文章理解が必要です。また、2級や1級は、それぞれ高度な漢字能力が求められ、専門的な文章や漢字、古典なども含まれます。
これらは一般的な目安であり、漢検の受験級は個々の学習状況や目標によって異なります。受験する際は、自分の持つ漢字能力や目指す級に合わせて適切に選ぶことが重要です。
漢検を受けるメリット
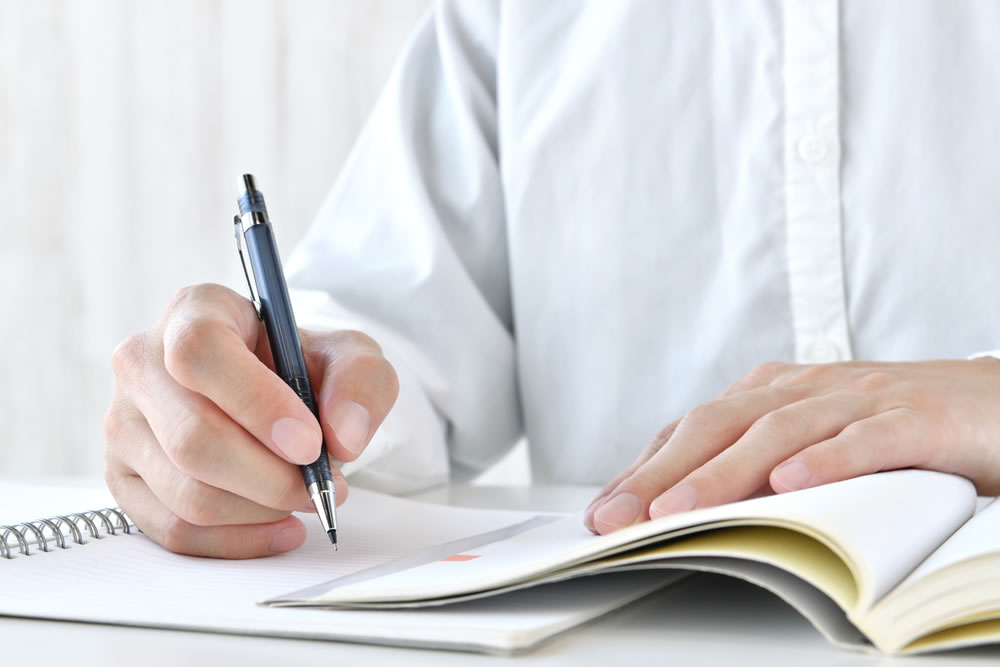
漢検は級が上がるほど難しくなりますが、漢字の能力を測定する以外にもさまざまな面で学習や成長に貢献する検定です。そのため、漢検を受験することは多くのメリットがあるのでチェックしましょう。
漢字力が向上する
漢検は、漢字の読み書き能力を伸ばす手助けとなります。試験勉強を通じて、様々な漢字や使い方を学ぶことで、語彙力や表現力が向上します。さらに、質問の意図を理解して自分の意見を的確に言葉にする力にもつながるため、面接試験でも役立つでしょう。
自己成長につながる
漢検は段階的な級が用意されており、合格することで次のレベルに進むことができます。努力をして目標を達成すれば、合格のたびに成長を実感できるので自信も得られます。
就職や進学が有利になる
漢検の合格証や取得級は、資格やスキルの一つとして認められるので就職活動や入試に有利です。また、漢字は就職試験や国語の試験で出題されるので、正確な漢字を書けるということも、就職や進学のプラスになります。
日本語力の向上に役立つ
漢検は、日本語の理解力を高めることが可能です。問題の文章や意味を理解することで、読解力や表現力がアップします。日本語力の上達は、学業はもちろんコミュニケーション能力の向上にもつながるでしょう。
学習習慣を定着させられる
漢検の合格を目指すことは、定期的な学習習慣を身につけるきっかけにもなります。漢字の勉強は継続的な努力が求められるので、スケジュールの管理能力や集中力を養えます。
新たな知識を習得できる
漢検を通じて、日本の文化や歴史に触れる機会が増えます。古典的な漢字や四字熟語、ことわざなどを学ぶことで、新しい興味や知識を得られます。
漢検は単なる試験ではなく、将来のための重要なステップになります。自己成長や日本語能力の向上に加えて、学習習慣の定着や新たな知識の習得、就職や進学の武器になるため多くの面でメリットを得られるでしょう。
漢検は何級以上で入試に有利?
一般的に、漢検で入試が有利となるのは3級以上で、2級以上となればさらに入試での有利性を発揮します。大学受験を意識するのであれば、「準2級」「2級」レベルを目標にして受検しましょう。2021年の公益財団法人日本漢字能力検定協会の調査では、入試で漢検の資格を評価する学校は全体の55%となっています。得点換算や試験の一部免除といった大学もあり、推薦入試においてもアピールが可能となる資格です。
ここでは、3級以上の特徴と有利性を解説します。
3級の有利性
漢検3級は、中学校卒業レベルの1,623字が対象です。3級取得は、一般的な日常生活や学校で使われる漢字を十分に理解し、読み書きができることを証明します。ただし、あくまで初級段階であり、最低限取得しておくべき級なので、入試に活かすには2級以上を目指すのがベストです。
準2級の有利性
準2級は、高校在学レベルの1,951字が対象漢字となり、入試に有利に働きます。高校入試では直接得点がプラスされたり、内申点の評価が上がったり、合否の判定として活用されることもあります。大学受験を意識するのであれば、「準2級」「2級」レベルを目標にして受検しましょう。
2級の有利性
漢検2級は、高校卒業・大学・一般レベル2,136字が対象となるため漢字の出題範囲が広く、専門的な内容や高度な漢字も含まれます。2級を持っていると、漢検を評価する企業や学校であれば就職活動と入試で加点が期待できます。
準1級の有利性
漢検準1級は、大学・一般レベル約3,000字が対象です。2級に比べると約950字も出題範囲が増えるため、さらに高度な知識が求められます。準1級に合格すると、常用漢字以上の漢字の知識が身についていることが証明され、進学や就職・転職でもアピールポイントになります。
1級の有利性
1級は漢検の最上級であり、非常に高度な漢字能力が求められます。1級を取得すると、高難度の専門知識や古典的な漢字、複雑な文章にも対応できることが証明されるため、入試や就職でかなり有利になるといえるでしょう。特に、学術や文学などの分野を目指している方は、取得しておくことをおすすめします。
漢検に向けた学習もサポートしている個別指導塾

漢検は、漢字に関する学力を高めるのはもちろん、入試でも役立つためチャレンジする価値があると言えます。漢字が苦手だったり、文章の読解力に自信がなかったりする場合でも、漢検に取り組めば自然に学力も向上していくでしょう。
漢検の勉強法は、繰り返し問題集に取り組む、漢検アプリで学習するなどいろいろありますが、地道な学習なのでお子様だけでは続かないかもしれません。代々木個別指導学院では、一人ひとりに合わせた「キミ専用カリキュラム」を用意しているので、漢検に向けた学習もサポートします。無料体験も実施しているので、「漢検も含めた受験対策をしたい」「個別指導に興味がある」という方はぜひ体験してみてくださいね。
代々木個別指導学院は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に85校あります。