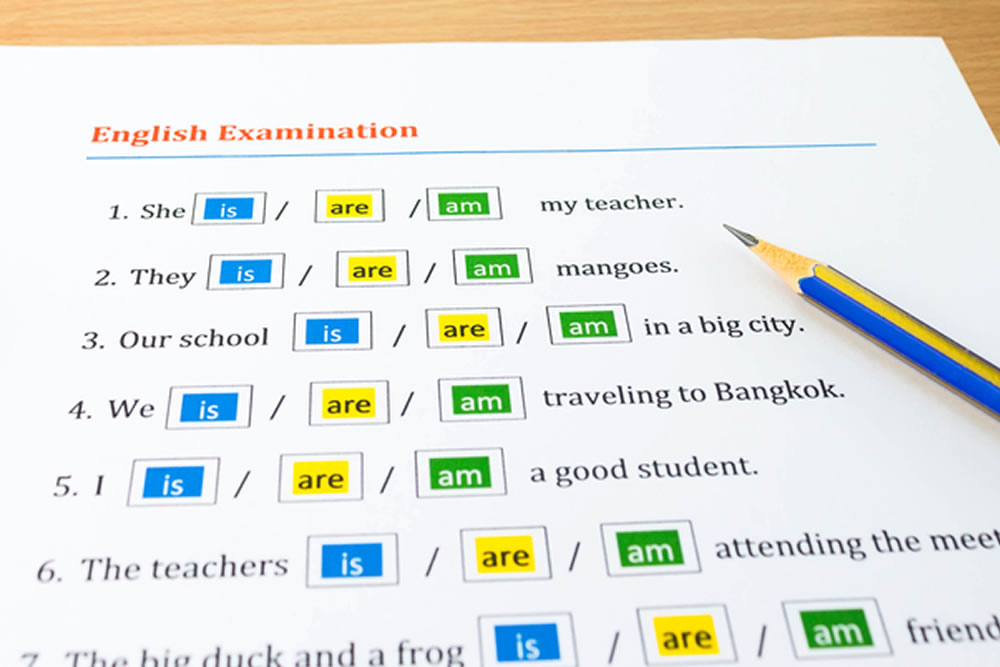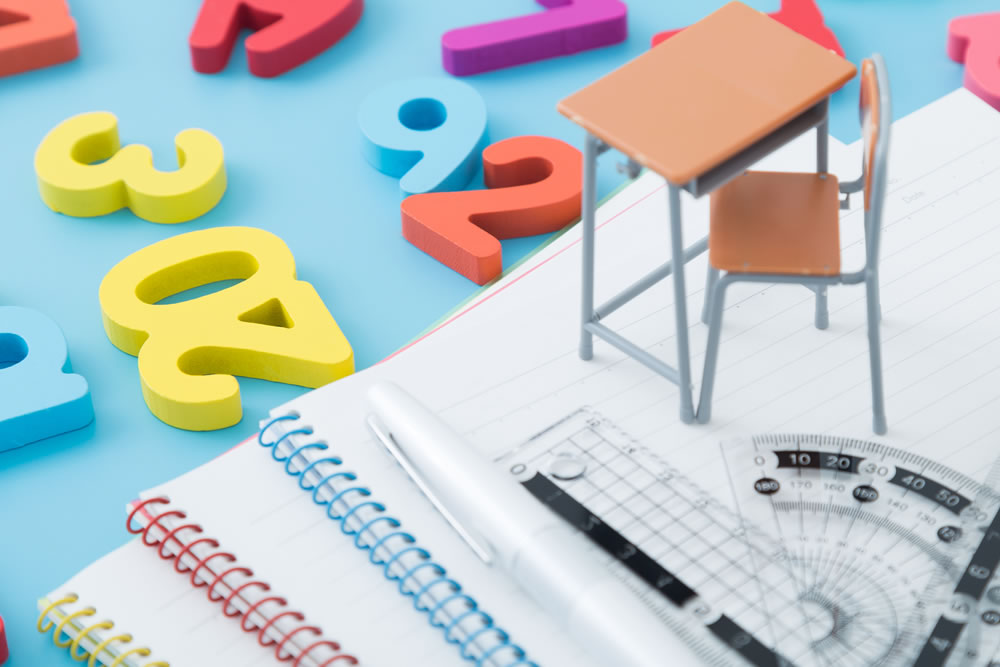このページは約 12 分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
目次
中学生になると、小学生の頃とは異なり学習の内容がより専門的なものへと変化します。
「算数とは違って、数学になった途端に勉強についていけなくなった」、「英語の授業が本格的になり、なんとなくしかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
クラス全員で歩調を合わせて勉強していた小学生の頃の授業とは異なり、中学生になると予習・復習は各自で済ませていることを前提に、早いペースで学習が進みます。
学習量も大幅に増えるので、中学生に合わせた正しい学習習慣を身につけていないと、受験生になった時に大きくつまずいてしまう可能性が高まります。
そこで今回は、中学生が身につけておきたい学習習慣を3つご紹介します。
受験生になるのが不安な方や受験生として伸び悩んでいる方、そして中学生のお子さんをもつ保護者の方は、ぜひ参考になさってください。
【注目!】中学生に人気の無料体験・資料請求のご予約はコチラから⇒
中学生の学習習慣①自分に合った学習習慣を見つけよう

クラスの全員が足並みを揃えて学び、全員が同じ理解度に達することを目的として授業が行われてきたのが、小学校での授業です。
一人ひとりの授業中の様子を担任の先生が丁寧に見回り、学習が遅れがちな生徒に合わせてゆっくりと授業を進めてくれていたイメージの方も多いのではないでしょうか。
しかしながら中学生になると学習内容が専門的に深まり、学習量も全体的にボリュームアップしていきます。
授業も先生のペースでどんどんと進んでいきますので、理解度の定着を図る手段は主に定期テストという形へと変化します。
そこで重要になってくるのが、自分に合った学習習慣です。
中学生の勉強では、自分自身のペースとやり方で、限られた時間のなかでも効率よく結果に結びつく学習を行っていく必要があります。
【おススメ関連コラム】中学生のテスト勉強の効果的な計画表の作り方を解説
必ず行いたい「予習」と「復習」
先ほどご説明した通り、中学生になると学校の授業がハイペースで進みます。
わからない人に合わせて授業のスピードを緩めてもらえるわけではなく、予習・復習を各自で済ませていることを前提として授業は進んでいきますので、家庭学習の時間を上手く活用することで、中学生の学習内容にアジャストしていく必要があります。
- 授業の前日に教科書を読み、わからない単語は意味を調べておく
- 帰宅後は授業内容を確認し、理解できていない部分はもう一度学習する
- 間違えた小テストを必ず解きなおす
このような習慣を身につけておくことで、学校の授業内容のなかで理解できていない部分をなくしていくことにつながり、受験生にとって必須の基礎学力を養うことにつながります。
「わからない」「たぶんわかった」を残さない
中学生の学習内容は、1年生でしっかりと固めた基礎を2年生・3年生でより発展させていく仕組みになっています。
そのため、ひとつでも理解できていない部分があると、応用問題を解く力が足りなくなってしまいます。
わからないというだけではなく、「わかったつもり」や「なんとなくわかった気がする」という状態にも注意が必要です。
「なんだかよくわからなかったけど、学校の授業が次に進んでしまったから、まぁいいや」
「わからない部分があるけど、みんなの前で質問するのは恥ずかしい」
「何回かやってみると解けたから、たぶんわかったと思う」
このように理解できなかったポイントを残したままにしていると、受験生になってから基礎のやり直しという絶望的なタイムロスが生じてしまう可能性があります。
「わからない」「わかったつもり」は中学生の勉強の大敵です。
苦手な単元に関してはゆっくりなペースでも問題ありませんので、必ず「わかったつもり」が「絶対できる!」に変わるまで、繰り返し学習していきましょう。
「できる!」はどんどん深めよう
先ほど「わかったつもり」を残さないことが中学生の勉強では大切とご紹介しましたが、反対に自分が興味のある分野、また「できる」「得意」と感じている教科に関しては、どんどん応用問題にチャレンジしていきましょう。
自分の得意分野を伸ばしていくことで、テストでいい点を目指すだけでなく、高校入学後の文理選択やその後の進路選択にも道が拓けるかもしれません。
もっと学びたいと感じている教科や単元は、積極的に問題集などを活用して学びを深めることをおすすめします。
【おススメ関連コラム】中学生で集団塾に向いている生徒と向いていない生徒の違いとは
中学生の学習習慣②宿題・提出物・定期テストに対して丁寧に取り組もう

受験生になり、進路を考えるときに後悔してしまう方が多いのが「内申点」です。
令和の現在、推薦入試のみならず一般入試にも内申点(調査点)が必要になります。
受験生として学力検査対策の学習を頑張ることも大切ですが、内申点で涙をのむことのないように、しっかりと準備していく必要があります。
スマホやゲームとの向き合い方も考えよう
中学生になると、友達とスマホで連絡をとったり、ゲームで対戦したりする時間が貴重な息抜き時間になっているという方も多いのではないでしょうか。
適度な時間でスマホやゲームを楽しむことはいい気分転換になりますし、現代では友人関係を維持するために欠かすことのできないツールのひとつでもあります。
またスマホを使って音楽を聴きながら勉強しているという方や、わからない問題の調べものにスマホを使うこともあるでしょう。
ただしスマホやゲームを使っている時間は、受験生として必要な勉強に直結する時間ではないことを忘れてはいけません。
「平日は1時間、休日は2時間しかゲームはしない」
「勉強中は、友達からのチャットを表示しないようにする」といったルールを決めて、スマホやゲームと上手く向き合いながら勉強することが大切です。
【おススメ関連コラム】高校受験では塾はいつから通えばいいの?志望校に合格した先輩からのアドバイスも紹介
中学生が身につけたい学習習慣③「自分で考える」を意識しよう
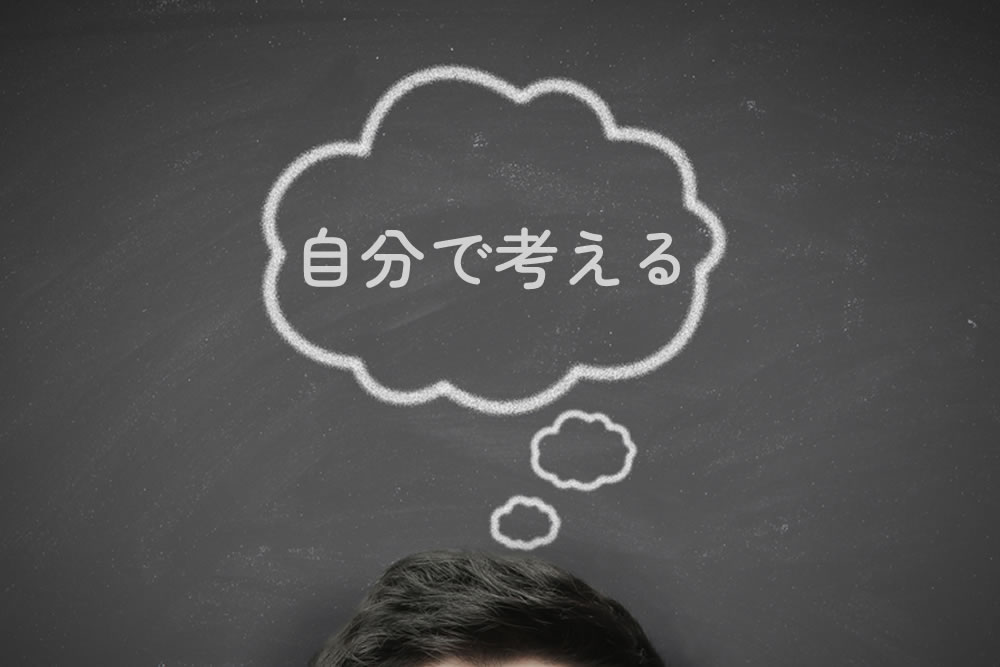
令和の時代の学習では、「自分の頭で考える」「自分の考えを文章として表現する」ということが重視されています。
令和3年度から導入された大学入試共通テストにおいても思考力を問う問題の割合が増えたことが話題になりましたが、グローバル化と価値観の多様化が進むこれからの社会では、自分の考えを持ち、そして行動する人こそ活躍できると考えられています。
そのため中学生のうちから自分の頭で考え、やり遂げる力を身につけることこそが重要なのです。
学習計画は自分で立てよう
中学生の勉強は、毎日の予習・復習、そして課題の提出と定期テスト対策が大切とご紹介しましたが、中学生は一人ひとりの状況によって、実際に勉強のために使うことができる時間数は異なります。
またそれぞれの得意・不得意によって、それぞれの教科ごとに必要な学習時間にも個人差が生じてくるのが中学生の学習の特徴です。
「部活動が朝晩ともに忙しいので、休日にまとめて予習・復習をしたい」
「短時間の勉強を毎日コツコツやるほうが、自分のスタイルに合っている」
「漢字は得意だけど、英単語は何度も繰り返す時間が必要」
勉強時間の配分や学習計画は一人ひとり違って当たり前。
大切なのは、自分の学習スタイルを理解して、自分に合った学習のペースを見つけて実践することなのです。
そのため中学生におすすめしているのは、自分のライフタイルと得意な科目・不得意な科目などを紙に書き出し、自分自身でペース配分を行いながら学習計画を考えてみることです。慣れないうちは1週間もしくは2週間おきに学習計画を見直すとよいでしょう。限られた時間を最大限に有効活用する習慣が身についていると、受験生になったときに効率よく学習を進めることができますので、とてもおすすめです。
反復練習で、知識の定着を図る
中学生の学習の難しさのひとつに、学習量の多さが挙げられます。
例えば小学生は6年間で1,006字の漢字を学習しますが、中学生が3年間で学習する漢字の数は1,130字となります。
もちろん学習量が増えるのは漢字だけでなく、英単語や数学の公式、日本史や生物・化学分野の勉強など、覚えなくてはいけないことが全体的に多くなります。
受験生になった時に知識に抜けている部分があると問題そのものを解くことができない可能性もありますし、知識だけをわかっている段階では「できる」というステップにまで到達することができません。
したがって中学生の学習では、何度も繰り返して問題を解くことで、本当に自分がその知識を習得できているのかを確認しておく必要があります。
定期テストが終わったからといって安心することなく、例えば長期休みのタイミングや、学年が上がるタイミングでは必ず今まで間違えた問題のやり直しを行うことを習慣にしておきましょう。
受験生になるための準備!中学生の学習習慣を正しく理解しておこう

高校受験は、中学1年生から3年生までの3年間で基礎から応用まで積み上げてきた全ての学習範囲を理解し、実力として発揮する必要があります。
受験生になったときに焦るのではなく、大切なのは中学生の3年間で正しい学習習慣を身につけておくことです。
①自分に合った学習の進め方を把握しておくこと
②宿題や定期テストに対してきちんと取り組むこと
③自分の頭で物事を判断し、行動すること
この3つの学習習慣を身につける意識を持ち、受験生としての勉強にスムーズに移行できるような下地作りに取り組んでいきましょう。
代々木個別指導学院は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に85校あります。