
このページは約 12 分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
目次
大学受験では、志望する大学や学部によって試験内容が異なります。
受験方法や日程もひとつではなく、生徒一人ひとりが自分の進路に向けてしっかりと準備をする必要があります。
大学入試に向けた準備のなかでも、近年特に注目を集めているのが「小論文試験(小論文)」です。
大学入試共通テストにおいては、記述式の問題導入が見送られたものの、各大学・各学部独自の小論文試験を設けて生徒の思考力や表現力を測るような流れがあります。
一般入試や理系学部においても小論文試験が課せられるケースは珍しくなくなっています。
そこで今回は、「大学入試で小論文が試験科目にあるけれど、書き方がわからない」という高校生に向けて、小論文の書き方や勉強法について、わかりやすく解説します。
【注目!】高校生に人気の無料体験・資料請求のご予約はコチラから⇒
小論文とは?小論文試験のポイントは?
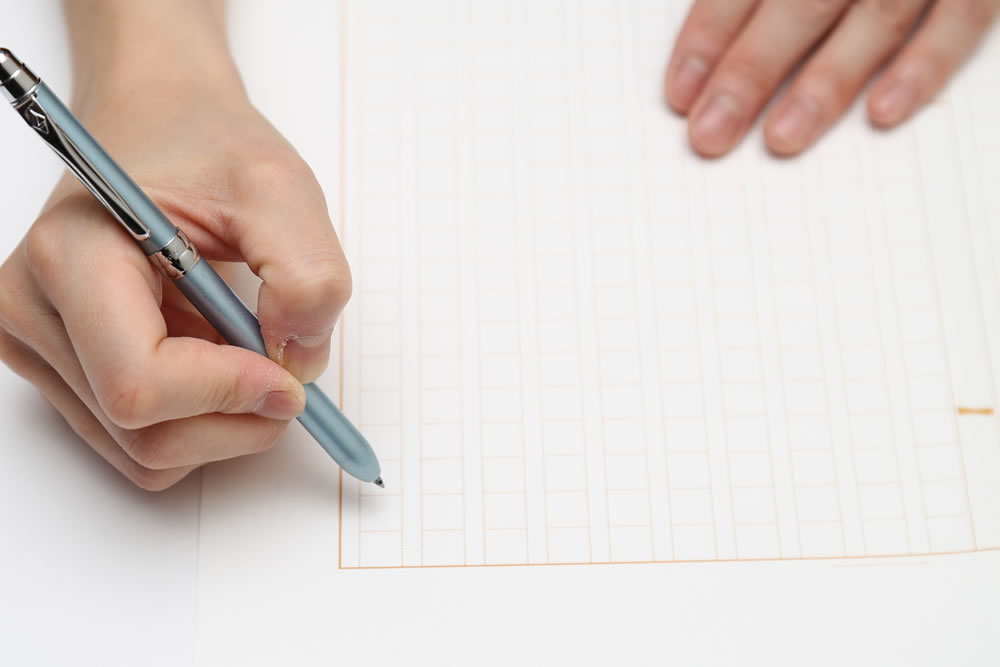
小論文は、自由に自分の思いや感想を書く、作文や感想文のような文章とは異なり、その名の通り「論理的に」自分の考えを表現しなければならない文章です。
「論理的」というと非常に難しいように感じてしまいますが、「第三者から見てもわかりやすいデータや根拠などを引用しながら、自分の主張を伝える内容に構成していく」というのが小論文の特徴です。
大学入試においては、600字〜1200字程度の文字数が指定されるケースが多く、原稿用紙の概ね3枚以内程度の文章を作成する必要があります。
※大学や学部によって文字数は異なります。必ず志望校の傾向を確認するようにしましょう。
【おススメ関連コラム】中学生のテスト勉強の効果的な計画表の作り方を解説
小論文の書き方
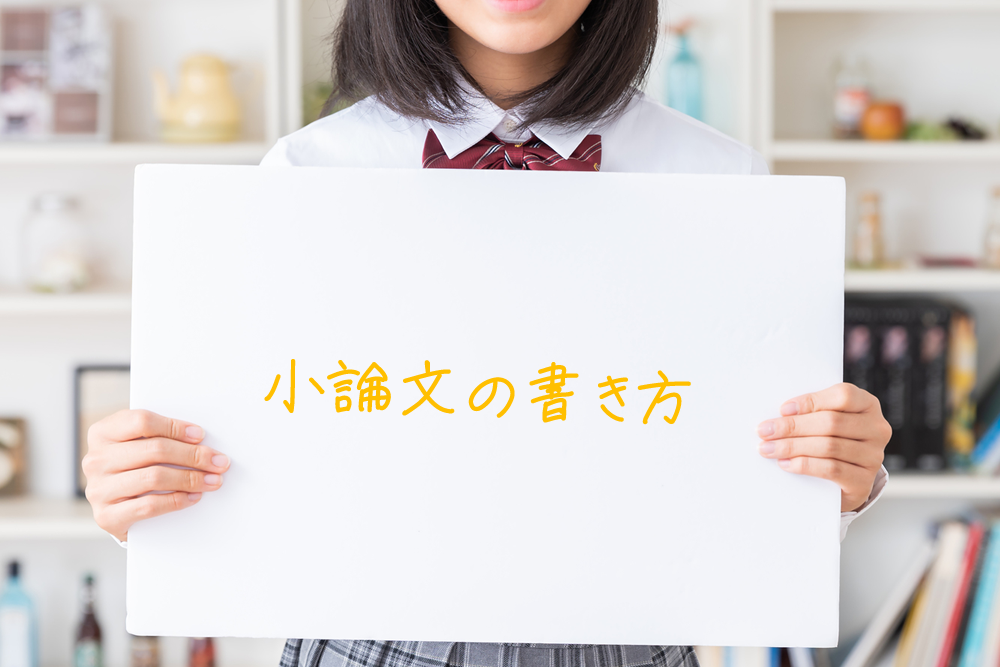
大学入試における小論文では、「原稿用紙の使い方」など、文章の基本も守ることが重要です。
とはいえ、文章の形式も、大学や学部によって異なります。
文学部などの一部文系学部では、これまで小学校や中学校で書いてきた作文や読書感想文のように、縦書きで記入するように指示されることがあります。
しかし、理系学部など、横書き指定が小論文試験の主流になりつつあります。
自分の志望校の過去の出題傾向を調べるなど、小論文の形式も確認しておきましょう。
横書き小論文の書き方
原稿用紙が横書きになった場合、段落の初めを一マス空ける・行頭に句読点が来ない(前行の最後のマスに文字と共に書く)といったルールは、縦書きの場合と同じです。
しかし、横書き縦書きで独自のルールや「通則」があります。
- 横書きの場合はアラビア数字(ただし慣用句は漢数字)を用いる
- 縦書きの場合は漢数字を用いる
- 縦書きでアルファベットは固有名詞以外は基本的に使用しない
- 横書きでは大文字1マス(1文字)、小文字半マス(0.5文字)でカウント
など、細かなルールが存在します。
小論文の書き方やルールを認識できていたとしても、実際に小論文を書いてみると、ルールを間違えてしまったり、ルールに気を取られて内容がわからなくなってしまったり、思うように書けないという状態になることがあります。
どんなに内容が素晴らしい場合であっても、小論文の書き方が間違っていると減点されるケースもありますので、小論文の書き方の基本を改めて確認しておくことが大切です。
小論文の構成
大学入試において、小論文の構成をする場合には、「序論・本論・結論」の構成を理解することが大切です。
まず簡潔に序論を書きます。
序論だけ読んだとしても小論文で伝えたいことが大まかに理解できるよう、簡単なまとめを導入文として書いていきます。
次に、本論を書いていきます。
本論は自分の考えを裏付ける客観的なデータを紹介したり、逆の意見に対する反論などを書くことによって、小論文の内容を濃いものに仕上げていく大切な部分になります。
本論部分はしっかりとボリュームを出して書きましょう。
最後に書くのが、結論です。
結論と序論がほぼ同じ内容になってしまうという生徒も少なくありませんが、結論と序論には変化をつけることがポイントです。
言い回しを変えたり、本論で紹介したデータを活用するなどして、小論文全体の内容をまとめていく必要があります。
全体的に序論:本論:結論が1:8:1程度になると、小論文としてのバランスが整います。
もちろん、内容によっては、序論:本論:結論が1:7:2になることもありますので、あくまでも基本の型としてイメージしておきましょう。
小論文の文字数
小論文試験では、文字数の指定に従って執筆しなくてはいけません。
「●●文字以内」の場合には指定文字数の9割以上、「●●文字程度」の場合は指定文字数に±1割程度、「●●文字から▲▲文字の範囲内」の場合はその指示に忠実に従うなど、出題文に合わせた執筆が必要です。
文字数の過不足は減点となる可能性がありますので、要注意です。
小論文のテーマ

大学入試の小論文で出題されるテーマは、大学や学部によって様々です。
とはいえ、大学や学部によって、毎年出題されるテーマには傾向がありますので、志望校の過去問をしっかりと把握しておくことが大切です。
大学入試小論文で狙われやすいテーマ①:時事問題・社会問題
大学入試頻出の小論文テーマとして挙げられるのが、時事問題や社会問題です。
特に、SDGsに関連する環境問題やジェンダーに関する問題、国際社会で起こっている様々な社会課題に関する内容が頻繁に出題されています。
テーマに関する短い出題があり、自分なりの意見を述べるというのが試験の基本形式になります。
問題と共にデータやグラフが示されている場合もあり、グラフなどから読み取れることも踏まえて、感情論ではなく論理的な視点から文章を構成し、第三者の共感を得られる文章を作成する必要があります。
大学入試小論文で狙われやすいテーマ②:特定の課題文の感想
提示された課題文を読み、自分の意見を述べるような形式の小論文もあります。
社会問題・時事問題に関連した課題文の場合もあれば、著名人の著書やスピーチからの引用が課題文として提示されることもあります。
いずれの場合であっても、作文や感想文を書くのではなく、課題文に対して自分の考えを丁寧に筋道立てて述べることが大切です。
課題文の主張への反論や共感などを論理的に説明することが大切です。
小論文試験の意図
そもそも、大学入試において、小論文試験は何のために実施されるのでしょうか。
大学側は、小論文試験を行うことで、受験生の問題を読み取る力(読解力)・考える力(思考力)・文章をまとめる力(構成力)・文章を書く力(表現力)といった能力を総合的に判断したいと考えています。
そのため、小論文試験がある大学や学部の受験を希望している場合には、一般的な学力試験に対する準備を進めながら、並行して小論文を書く練習に取り組み、読解力・思考力・構成力・表現力を育んでおかねばなりません。
大学入試の小論文対策は独学が可能?

ここまでで、小論文試験の概要と小論文対策の重要性についてご紹介しました。
大学入試において年々重要度が増す小論文試験ですが、小論文対策を生徒が独学で行うことは難しいです。
独学の小論文対策が難しい理由
独学での小論文対策が難しい理由として、「小論文の書き方や内容に関する間違った認識は自分自身では修正しにくい」という点が挙げられます。
自分で書いた文章のミスにはなかなか気が付きにくいので、第三者に指導してもらいながら学んでいくことが重要です。
小論文は第三者に向けて書く文章であるため、独学での学習がとても難しいです。
作文のように自分の体験や感想を自由に綴れば良い訳ではなく、意見と理由をわかりやすくまとめ、他人から見ても納得のできる内容に仕上げる必要があります。
そのため、第三者に小論文をチェックしてもらい、理解できる構成や文章になっているか、改善点はどこかを指摘してもらわないと、なかなか小論文としてのレベルを上げていくことは難しいです。
【おススメ関連コラム】内申点を上げたい中学生におすすめな勉強法とは?
小論文対策は個別塾がおすすめ!

自分ひとりでは難しい小論文対策だからこそ、プロのサポートや指導を受けることがおすすめです。
大学入試に向けて小論文対策を行うのであれば、現在の小論文執筆能力・学力考査の学習状況・志望校や志望学部の受験科目・高校の定期テストの状況などをトータル的に判断した上で、小論文対策のカリキュラムを作成する必要があります。
そのため、大学入試の小論文対策を行うためには、生徒一人ひとりに対してオーダーメイド型のカリキュラムを提供することができるような個別塾でアドバイスを受けましょう。
小論文の書き方なら代々木個別指導学院にお任せ!

代々木個別指導学院は、大学入試に向けた小論文試験の対策はもちろん、生徒一人ひとりに対してピッタリの大学入試対策をトータルサポートしております。
各校舎に総合学習アドバイザーが在籍しており、生徒一人ひとりにあったカリキュラムを作成しています。
小論文対策に関しても、生徒の実力や志望校(志望学部)に合わせてカリキュラムに組み込んでいきますので、定期テストや大学入学共通テストの準備も怠ることなく、きっちりと小論文対策も行うことが可能です。
厳選された講師陣が基本的な小論文の書き方を指導するのはもちろんのこと、高得点を狙える例文やテクニックを指導しますので、自信をもって小論文試験に挑戦できるようになります。
大学受験の小論文対策は代々木個別指導学院に相談!

小論文試験は事前の準備が非常に重要です。
代々木個別指導学院では、無料の入会カウンセリングを通して、生徒一人ひとりに合わせた学習カリキュラムのご紹介と最新の大学入試情報のご案内を行っています。
もちろん、体験授業にも無料で参加可能ですので、代々木個別指導学院の小論文対策に納得した上で、通塾を決めていただくことができます。
大学入試に向けて小論文の書き方や、効率的な対策が知りたいという生徒は、お近くの代々木個別指導学院までお問い合わせください。
代々木個別指導学院は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に85校あります。


















